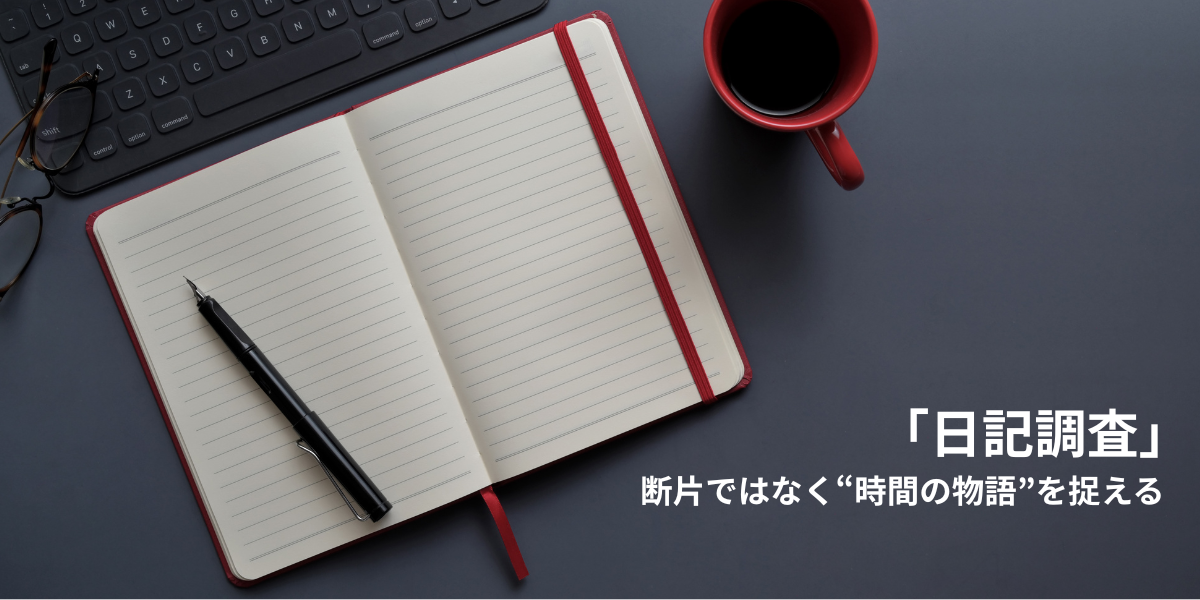あの「やる気」は、なぜ続かないのか?
「AIが、あなただけの専属トレーナーに」
そんな魅力的な触れ込みの新しいフィットネスアプリ。あなたは意気揚々とダウンロードし、最初の数日間はAIからの励ましを楽しみながら、順調にトレーニングをこなします。もしこの時点で誰かに感想を聞かれたら、きっと「最高のアプリです!これなら続けられます」と絶賛していたはずです。
しかし、一週間後。 仕事の疲れが溜まった水曜日の夜、あなたは「今日だけは…」とトレーニングを休みます。一度途切れた習慣は、なかなか元には戻りません。アプリの通知は、いつしか罪悪感を刺激するだけの存在に。そして2週間後、あのAIトレーナーは、スマホの片隅で静かに眠っています。
この、誰もが経験する「三日坊主」という現象。 その裏側には、ユーザーのモチベーションを少しずつ削いでいく、日常の小さな出来事が隠れています。なぜ熱狂が冷め、利用が途絶えてしまうのか。その「なぜ」の答えに、ユーザーの日常に寄り添いながら迫っていくUXリサーチ手法が、日記調査です。
日記調査とは?
日記調査とは、ユーザーに一定期間、日常生活の中での行動、思考、感情などを、自ら記録してもらう調査手法です。
なぜ、わざわざ日記形式で記録してもらうのでしょうか?それは、人の記憶が驚くほど曖昧で、偏っているからです。心理学者ダニエル・カーネマンが提唱した「ピーク・エンドの法則」によれば、人は自らの体験を、感情が最も高ぶった瞬間(ピーク)と、最後の瞬間(エンド)の記憶だけで評価する傾向があります。インタビューで語られる「楽しかった」という感想は、しばしばこのピーク・エンドの記憶に強く影響されているのです。

では、習慣化を阻んだ日々の小さな「つまずき」や「面倒くささ」はどこへ行くのでしょうか?それらは、強烈な記憶に埋もれ、忘れ去られてしまいます。日記調査は、この記憶のバイアスを乗り越え、日々の断片をリアルタイムで記録するための、極めて実践的なアプローチです。それは、ユーザーの体験を「点」としての記憶ではなく「線」としての時間の流れの中で捉えようとする試みとも言えるでしょう。
AIトレーナーは、なぜ2週間で使われなくなったのか?
では、2週間の日記調査を通じて、冒頭のフィットネスアプリのユーザーの「時間の物語」を覗いてみましょう。そこから見えてきた「物語」の断片を、リサーチャーの気づきと共に見ていきます。
【1日目:期待】
日記の記述:
「箱のデザインからして最高!セットアップも驚くほど簡単だった。睡眠スコアを測るのが今から楽しみ。」
リサーチャーの気づき:
初期体験は完璧。ユーザーのモチベーションは最高潮に達している。

▼
【4日目:最初の壁】
日記の記述:
「今日は残業でヘトヘト。AIからの『トレーニングの時間です!』という通知が、正直ちょっと重たい…。今日は休んで、明日2倍頑張ろう。」
リサーチャーの気づき:
初めての「疲労」という文脈との衝突。ポジティブだった通知が、状況によってはプレッシャー(心理的負荷)に変わることがわかる。
▼
【8日目:習慣の競合】
日記の記述:
「金曜の夜。友達から飲みに誘われて、トレーニングはお休み。罪悪感はあるけど、やっぱり人付き合いも大事だし…。」
リサーチャーの気づき:
「友人との交流」という、より優先度の高い習慣が発生。アプリは、ユーザーの生活の中にある無数の習慣と、常に可処分時間を奪い合っているという現実が浮かび上がる。
▼
【12日目:自己流の最適化】
日記の記述:
「毎日30分のトレーニングは無理だと悟った。でも、朝起きてすぐできる『5分ストレッチ』だけは、意外と続いている。これだけでもやらないよりはマシかな。」
リサーチャーの気づき:
ユーザーは、当初想定されていた使い方を諦める一方で、自分なりの、負担の少ない使い方(=5分ストレッチ)を発見し、習慣化しようとしている。ここに、離脱を防ぐための重要なヒントが隠されている。
「課題発見」だけではない、日記調査の活用シーン
この記事では、主に「なぜ継続利用されないのか」という課題発見の例をご紹介しました。しかし、日記調査の活用範囲はそれだけではありません。
例えば、以下のような目的でも非常に効果的です。
- 初期体験のジャーニーを追う:
新製品のUnboxing(開封)からOnboarding(初期設定)、そして最初の数日間の利用体験までを時系列で追い、ユーザーがつまずきやすいポイントや感動する瞬間を詳細に捉える。 - オムニチャネルでの購買行動を理解する:
SNS広告で商品を知り、店舗で実物を確認し、最終的にECサイトで購入する、といった複数のチャネルをまたぐ複雑な購買プロセスを、ユーザーの視点で一気通貫に理解する。
このように、日記調査はユーザーの長期的な行動や、複数のタッチポイントが絡む体験を理解する上で、他に代えがたい価値を提供します。
日記調査を成功させる3つのポイント

日記調査はとても効果的な手法ですが、ユーザーに負担をかけるため、成功には丁寧な設計が不可欠です。
ポイント1:最適な「記録方法」を選ぶ
ユーザーの負担を減らし、欲しい情報を的確に得るためには、ツールの選択が重要です。目的別に、以下のような選択肢が考えられます。
気軽に投稿してもらいたい時 → LINEなど日常のチャットアプリ
写真一枚と一言、といった気軽な投稿を集めやすいのが特徴です。ユーザーの心理的ハードルを最も下げられます。
定型的な回答を集めたい時 → Googleフォームなど簡易アンケート
「今日の満足度は?」といった定量データと、自由記述をバランス良く組み合わせたい場合に適しています。
リアルな行動を映像で記録したい時 → 専用のリサーチプラットフォーム
製品の利用風景など、ありのままの状況を動画でリッチに集めたい場合に有効です。
ポイント2:「行動」と「感情」をセットで捉える
「何をしたか」だけでなく、「なぜそうしたか」、「どう感じたか」をセットで記録してもらうことが重要です。
例えば「今日は30分運動した」という事実に加え、「今日のモチベーションを5段階で評価してください」、「その評価の理由を教えてください」といった問いを組み合わせます。これにより、「疲れていたけど頑張った達成感」と「義務感でやった徒労感」といった、同じ行動の裏にある全く異なるインサイトを捉えることができます。
ポイント3:最後のインタビューで「物語」を完成させる
日記調査は、それ単体で完結するものではありません。調査の最後に行うインタビューは、集まった断片的な記録を、意味のある一つの物語へと昇華させるための重要なプロセスです。日記の記録をユーザーと一緒に見返しながら、「この8日目、お友達と飲みに行ったと書かれていますが、この時アプリのことは思い出しましたか?」といった具体的な質問を投げかけます。ユーザー自身の記録をトリガーにすることで、本人も忘れていたような深い価値観や、習慣化を阻む根本的な障壁が明らかになるのです。
まとめ:ユーザーの「時間の物語」から、ビジネス成功の分岐点を見つけ出す
日記調査は、ユーザーの「点」としての声ではなく、「線」としての日常に寄り添い、ユーザー体験が時間と共にどう変化するのかを明らかにします。この手法は、特に海外のユーザーを対象とする際に、その真価を発揮します。インタビューだけでは見えない、現地の文化や生活習慣に根ざしたリアルな行動(例えば、日本では想定されない製品の使い方や、家族との関わり方など)を捉えることができるからです。
ユーザーの「時間の物語」を可視化すること。それは、ユーザーが体験の中でつまずき、あるいは感動する分岐点を見つけ出し、サービスが成長するための本質的なインサイトを掴むことに他なりません。
Uismでは、国内はもちろん、海外での日記調査も数多く手がけてきました。幅広い領域において、ユーザーの行動変容や習慣形成の課題を明らかにしてきた豊富な実績があります。「アンケートでは好意的なのに定着しない」、「ユーザーがなぜ途中で離脱するのか見えていない」と感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
その他調査手法紹介の記事: