先日、東京都美術館で開催されているゴッホ展を訪れました。展示室の静かな喧騒の中、彼の描いた人物画や風景画と向き合っていると、以前に読んだ、ある哲学者のエッセイのことが頭をよぎりました。
そのエッセイが題材にしていたのが、ゴッホが描いた一足の古びた「農民の靴」でした。哲学者のマルティン・ハイデガーは、かつてこの絵を見て、単なる靴ではなく、それを使う農民の「世界」そのものが現れている、と論じました。農民にとって、その靴は意識さえされない透明な道具ですが、絵の前に立つ私たちにとっては、その人の人生を物語る雄弁なモノとして存在している、と。ゴッホ展を訪れたことで、私はこのハイデガーの言葉を改めて思い出しました。
そして、その思索は自然と、私たちの仕事であるUXデザインへと繋がっていきました。
最高のUXとは、ユーザーがその存在を忘れ、自らの目的(=世界)に没入できる「透明な道具」になることではないでしょうか。この記事では、先日訪れたゴッホ展での思索をきっかけに、ハイデガーの哲学をレンズとして、私たちが目指すべき「消えるデザイン」の本質について考察します。少し哲学的な話から始まりますが、皆さんが毎日使っているアプリの使いやすさの本質に迫る、とてもシンプルな話です。

道具の二つのあり方:ハイデガーのハンマー
ハイデガーは、道具が持つ二つの異なる存在の仕方を、大工が使うハンマーを例に説明しました。
- 道具的存在(透明な道具):
熟練の大工がハンマーで釘を打つとき、彼の意識は「ハンマーを握っている」ことにはありません。彼の意識は、ただ「釘を打ち込む」という目的に向かっています。ハンマーは彼の手の延長となり、その存在は意識から消え、作業の世界に溶け込んでいます。 これが、道具が本来あるべき姿、「道具的存在」です。 - 事物的存在(意識されるモノ):
しかし、もしそのハンマーの頭がぐらついていたらどうでしょう。大工は釘を打つ作業を中断し、「このハンマーは壊れている」と、ハンマーそのものを一個のやっかいなモノとして意識せざるを得ません。作業の世界から切り離され、目の前に現れる。これが、道具がその機能を失った姿、「事物的存在」です。
UXデザインの本質
実はこのハイデガーの思想こそが、後にドン・ノーマンをはじめとするUXデザインの第一人者たちが提唱する「見えないデザイン(Invisible Design)」の、哲学的な源流となっているのです。「最高の道具とは、ユーザーに意識されることなくタスク達成を助けるべきだ」というハイデガーの思想は、一世紀近くも前のものとは思えないほど、現代のUXデザインの本質を的確に捉えています。この「道具的存在」と「事物的存在」という二つのモードは、そのまま優れたUXと、劣悪なUXの対比に当てはまります。
優れた地図アプリを使っている時、私たちはUIのボタン配置や配色を意識しません。ただ目的地のことだけを考え、いつの間にか到着しています。お気に入りの音楽ストリーミングアプリでプレイリストを流しているときも同じです。私たちの意識はアプリの操作ではなく、音楽そのものと、それが呼び起こす感情や風景にあります。 アプリは「道具的存在」として機能し、私たちの意識の中から“消えている”のです。
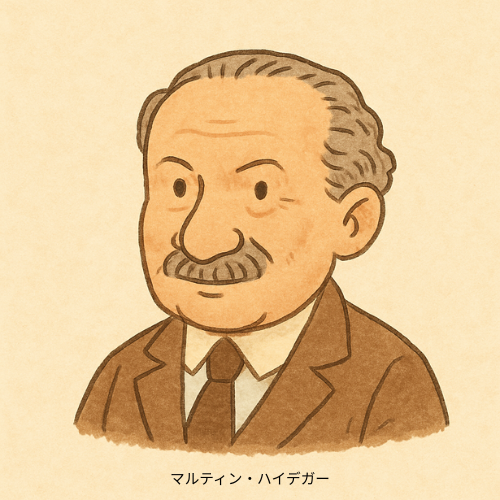
一方で、頻繁にクラッシュするアプリ、どこにあるか分からない機能、レスポンスの遅いインターフェース。これらに遭遇した瞬間、私たちは目的のタスクから引き剥がされます。アプリはもはや私たちの目的を助ける道具ではなく、それ自体が解決すべきやっかいなモノへと姿を変え、私たちの前に立ちはだかります。これこそが、ユーザーの不満やストレスの源泉です。
つまり、UXデザイナーの究極的な目標とは、自らがデザインした製品を、ユーザーの意識の中で可能な限り「道具的存在」であり続けさせること、すなわち「消えるデザイン」を設計することに他ならないのです。
「消えるデザイン」が私たちに教えること
このハイデガーの視点から、私たちはUXデザインにおける3つの重要な教訓を学ぶことができます。
1. 画面の向こう側にある「世界」を理解する
私たちがデザインすべきなのは、単なる美しい画面ではありません。ゴッホの靴が農婦の労働の世界と分かちがたく結びついていたように、私たちがリサーチで向き合う製品もまた、ユーザーの生活や仕事という「世界」の一部となります。その世界を深く理解しない限り、本当に「消える道具」を作ることはできません。これこそ、UXリサーチが不可欠である理由です。
2. 「摩擦」を削ぎ落とすことへの執念
不要なクリック、分かりにくい言葉、余計な選択肢。これらすべての「摩擦」は、ユーザーを没入から引き剥がし、道具を意識させてしまうノイズです。フリクションレスな体験を追求することは、製品を「透明」に保つための、極めて実践的なアプローチです。
例えば、Amazonの1-Click注文を思い浮かべてみてください。住所やクレジットカード情報を何度も入力させるという、購入プロセスにおける最大の摩擦を取り除いたことで、私たちは「商品を買う」という目的そのものに集中できます。あのボタンは、決済プロセスというやっかいなモノを、ユーザーの意識から限りなく“消した”好例と言えるでしょう。
3. 信頼性と安定性は、体験の土台である
バグやクラッシュ、予期せぬエラーは、道具を「道具的存在」から「事物的存在」へと転落させる、最も暴力的な行為です。製品の安定性は、単なる技術的な品質の問題ではなく、ユーザー体験の根幹を支える、最も重要なデザイン要素なのです。
おわりに
最高のデザインとは、その存在を声高に主張するものではなく、むしろ、ユーザーがその存在を忘れ、自らの目的を達成することに没入させてくれるものです。それは、まるで熟練の職人が作った、手に馴染む道具のように。UXデザイナーとは、この「透明な道具」を作り出す、現代の職人なのかもしれません。ユーザーの生活世界に敬意を払い、彼らがその人自身の物語を生きるのを、そっと背後から支える。
この記事で考察した「消えるデザイン」の実現は、ユーザーの「世界」を深く理解するリサーチから始まります。Uismでは、まさにそのためのUXリサーチをご支援しています。より豊かなユーザー体験の創造にご興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。
あわせて読みたい:
UXを「消えるデザイン」として捉えた本記事に続き、「人の自由や選択をどう支えるか」というもう一つの視点からUXを考える記事もぜひご覧ください。


