アクセシビリティという言葉は少しずつ日本でも広まりつつありますが、その理解はまだ一部の専門家や業界に限られている印象です。また、「配慮」や「アクセスのしやすさ」といった表面的な文脈で語られるケースもあり、UXやユーザー中心設計といった視点と、まだきちんと結びついていないのが実情です。
一方、欧米ではアクセシビリティは社会の前提として根付き始めています。特に注目されているのが「Co-design(協働デザイン)」というアプローチです。これは障がいのある方を「使う人」ではなく、「共につくる人」として迎え入れ、設計段階から関与してもらう考え方です。
この記事では、Co-designという考え方を簡単に紹介したうえで、そのアプローチを活かして開発された海外の支援アプリの事例をご紹介します。どのように共につくる姿勢がUXに活かされているのか、具体的に見ていきましょう。
Co-designとは何か?なぜ注目されているのか
どれだけ優れた機能に見えても、それが本当に役立つかどうかを判断できるのは、実際にその機能を使う人だけです。特に障がいのある方が日常で感じる困りごとは、健常者の想像だけでは捉えきれない部分が多くあります。
こうした見えにくいニーズを理解するために、UXリサーチが果たす役割は大きいものです。その中でも、ユーザーの声を聞くだけでなく、共に考え、共に手を動かしながら形にしていくという姿勢こそが、Co-designの本質です。 このアプローチは、従来のユーザビリティテストなどのように、製品がある程度できあがった後に評価を行うものではありません。設計の初期段階から当事者と共にアイデアを出し、構造を考え、形にしていくのです。
Co-designは探索的リサーチ(exploratory research)とコンセプト設計を同時に行う、実践的なUXリサーチ手法の一つとも言えます。例えば、以下のような取り組みが挙げられます:
- ワークショップで困りごとを共有しながら機能を考える
- ペーパープロトタイプで構造を一緒に描き出す
- 実際の生活環境でプロトタイプを試し、リアルタイムで調整する
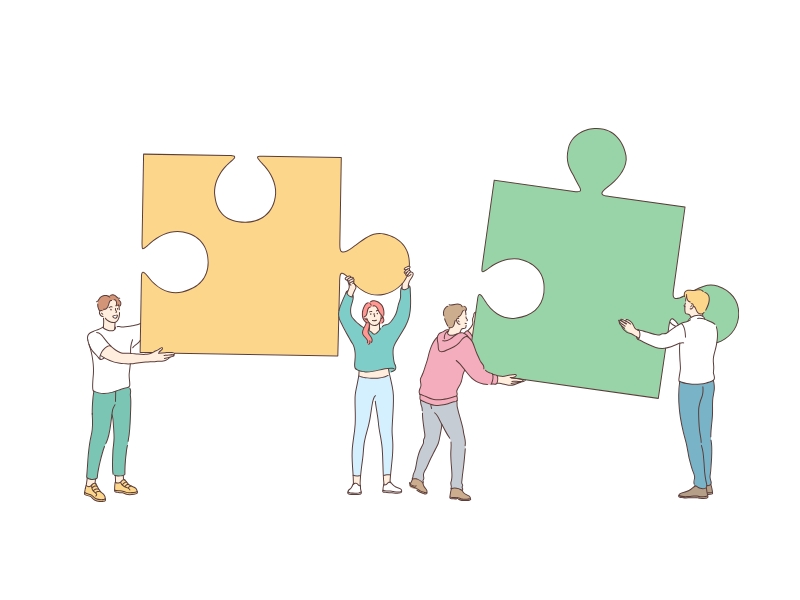
ユーザーとともに「どんな場面で困っているのか」、「その時、どんな情報があれば安心できるか」を洗い出し、画面設計や機能構成を一緒に考えることがCo-designであり、同時に設計そのものでもあるのです。
Co-designの恩恵を受けるのは障がい者だけではない
Co-designは、障がいのある方のためだけのものではありません。実際には、誰もが使いやすいUXを実現するための基盤として、多くの人に恩恵をもたらします:
- 障がいのある方:物理的・認知的なバリアを取り除き、平等な情報へのアクセスを提供する。
- 高齢者:加齢に伴う視覚・聴覚・運動機能の変化にも配慮された、やさしい操作設計にする。
- 一時的な障がいのある方:骨折や体調不良などにより一時的に制限がある場合でも、無理なく使えるよう配慮されたUIを提供する。
- 言語に不慣れな方:平易な表現や多言語対応により、内容の理解をよりスムーズにする。
- 読み書きに課題のある方:直感的なUIや視覚的な要素で、情報取得の負担を軽減する。
- 騒がしい環境での利用者:音声が聞こえにくい状況でも字幕やビジュアルで補完する。
- 通信環境が不安定な地域や状況:軽容量な設計や高速表示によって、ストレスの少ない操作にする。
- すべてのユーザー:一貫したレイアウト、直感的な操作性により、誰にとっても快適なUXを提供する。
このように、 Co-designを通じて生まれる設計は、特定の誰かのためだけでなく、すべてのユーザーにとっての使いやすさに繋がっていきます。
海外の障がい者向けアプリの紹介
次に紹介するアプリは、開発段階からユーザーが深く関与し、彼らの実体験やニーズをもとに磨き上げられてきたものです。Co-designがいかに実際の機能や使いやすさに反映されているかを、それぞれの事例から見ていきましょう。
視覚障がい者向けアプリ

視覚障がい者向けアプリ

聴覚障がい者向けアプリ

発話困難の方向けアプリ

肢体不自由な方向けアプリ

誰かにとっての当たり前を見直そう
スマートフォン1台で生活の質が大きく変わる現代において、アクセシビリティ設計の質は、社会インフラの一部だと私は思っています。特にアクセシビリティの領域では、机上の想像や一般的なユーザビリティテストだけでは限界があり、実際に困りごとを抱える当事者を巻き込んだリサーチこそが、役立つサービスを生み出す鍵となります。
Co-designを実践することによって、単なる「配慮」を超えた、アクセシビリティの本質的な価値が見えてきます。海外のアプリが優れたUXを実現し、成功しているのは、まさにその「共につくる姿勢」が一貫しているからでしょう。
アクセシビリティに限らず、誰かにとっての当たり前を問い直すことは、あらゆるUX改善の出発点となります。見慣れたものこそ見直す価値がある。そんな視点で身の回りを見つめ直してみると、新たな発見が得られるかもしれません。
私たちUismとともに「当たり前」の中に埋もれたヒントを見つけ、多様なユーザーにとって使いやすい体験を一緒に考えてみませんか?


