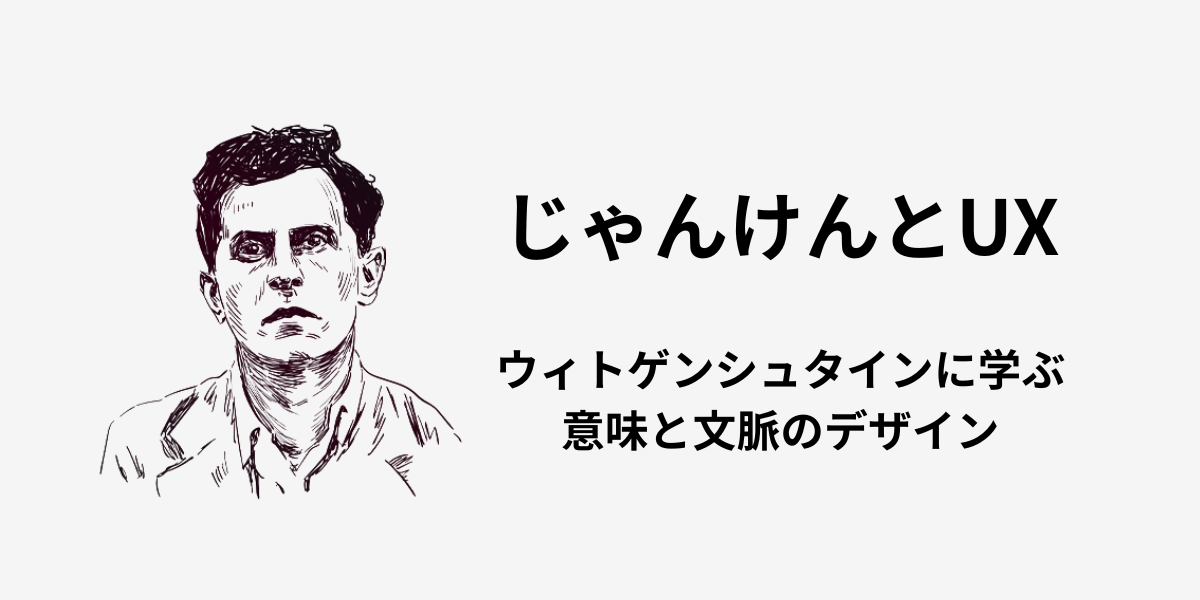ある日、子どもからふと聞かれました。
「なんで、じゃんけんって石と紙とはさみなの?」
たしかに。何気なくやっている「じゃんけん」ですが、その意味や成り立ちについて深く考えたことはありませんでした。 でもその瞬間、UXリサーチャーとしての探究心がくすぐられたのです。
なぜこの3つの手が選ばれたのか?なぜ、じゃんけんをすればお互い納得して勝敗が決まるのか?こんなシンプルな遊びが、どうやって文化として成立しているのか? そんな素朴な問いをきっかけに掘り下げていくと、思いがけず「ユーザー体験」や「言葉の意味」に関する深い発見につながっていきました。
じゃんけんのルーツ
じゃんけんの基本構造は、石(グー)、紙(パー)、はさみ(チョキ)という3つの手で、勝敗を決める三すくみ型のゲームです。この三すくみは、「蛇はカエルに強く、カエルはナメクジに強く、ナメクジは蛇に強い」など、民間信仰や自然観にも通じる、日本的なバランス構造を象徴しています。
じゃんけんの前身は江戸時代に流行した石拳(しゃっけん/じゃくけん)という手遊びで、中国の拳遊びが日本で独自に進化したものです。初期には「虎・銃・兵士」などのテーマもありましたが、時代を経て、子どもでも親しめる「石・紙・はさみ」へと定着しました。
地域・文化で異なる「じゃんけん」のかたち
また、おもしろいのは、じゃんけんが全国で通じるにもかかわらず、地域によって掛け声や進行方法が微妙に異なることです。
- 関東では「最初はグー、じゃんけんぽん」
- 関西では「いんじゃんでほい」
- 長崎では「しっしのし!」
- 鹿児島では「いーけーどん!」
掛け声だけでなく、手を出すタイミングや、あいこの処理ルールも地域ごとに違います。でも、子どもたちは混乱することなく、それぞれの地域で自然に遊んでいます。
また、日本国内だけの文化ではありません。日本から世界に広がり、英語圏ではRock, Paper, Scissorsとして知られ、欧米の子どもたちの間でも広く遊ばれています。さらに国によっては、手の形やモチーフが異なるバリエーションも存在します。
- 象・人・蟻(Elephant, Man, Ant)
- 石・布・はさみ(Stone, Cloth, Scissors)
このように、ルールの核となる構造は保ちつつ、表現や慣習が文化によってアレンジされているのです。
文脈が意味をつくる:「じゃんけん」とUX的視点
じゃんけんは、同じグー・チョキ・パーという構造を持ちながら、地域や国、場面によって進め方や意味が少しずつ異なります。こうした特徴は、UXの考え方にも深く関わってきます。
どういう意味でUX的なのかというと、まず、同じ構造がありながらも、文脈に応じて意味や使われ方が変わるという点があります。UXとは、ユーザーがどのような状況で、どのようにサービスや製品に触れ、どのようにそれを解釈して使うかという体験の全体を扱います。つまり、単なる見た目や機能だけでなく、使われ方やその場での意味づけに強く関心を持つ領域です。
じゃんけんは、地域ごとに掛け声やルールの細部が違っていても、全体としての遊びとしての意味が成立しています。それはまさに文脈依存性の高いUXが、柔軟な構造によって破綻せずに成り立っている例といえるのです。
また、じゃんけんにはマニュアルもチュートリアルもありませんが、誰でも直感的に理解し、使いこなせます。これも、UX設計におけるナチュラルなインタラクションや初見でも迷わない体験デザインに通じます。
UX的なポイントをまとめると:
- 文脈によって意味が変わる=文脈依存性
- 地域差があっても遊びが成立する=柔軟性と共通理解のバランス
- 誰でもすぐに理解して使える=直感的なインタラクション
哲学者ウィトゲンシュタインと「言語ゲーム」
このように、じゃんけんの構造は、状況や文化によって意味が変化しても、全体の体験として破綻しません。これは、「意味とは文脈によって生まれる」という視点から見ると、とても示唆的です。
このとき私の頭に浮かんだのが、哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの言葉です。彼の有名な主張に、「意味とは、言葉の使われ方である」というものがあります。つまり、言葉の意味は辞書的な定義ではなく、「どんな文脈で、どう使われているか」によって決まるという考え方です。
彼はこれを「言語ゲーム」と呼びました。人は、それぞれの状況や文化の中で、自然と使い方を学び、共有しています。
たとえば「グー」という言葉は石を指しますが、じゃんけんにおいては「チョキに勝ち、パーに負けるもの」というルールの中の役割を持っています。こうして考えると、じゃんけんは言葉を発しなくても成立する「非言語的な言語ゲーム」として捉えることもできるのです。
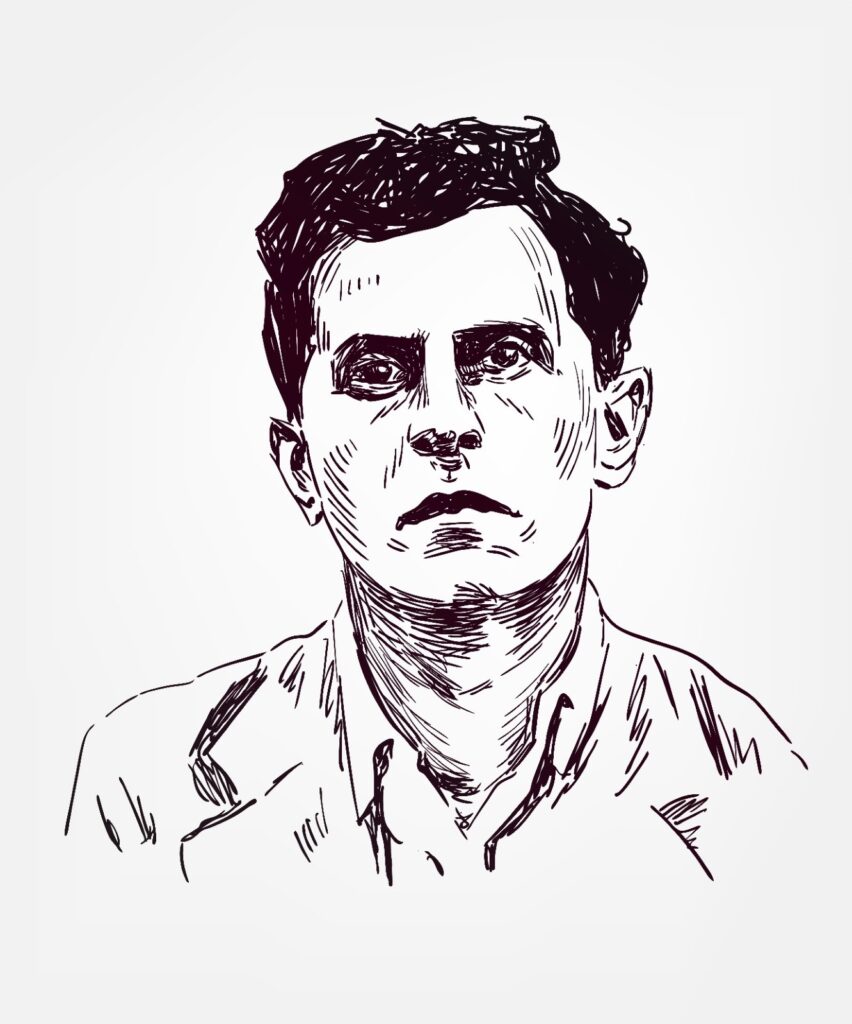
UXリサーチと「意味のズレ」
UXリサーチの現場でも、この「言語ゲーム」の視点は非常に役立ちます。というのも、私たちが扱うユーザーの発言や行動は、ほとんどが文脈依存だからです。たとえば、ある対象者が「このアプリ、使いやすいですね」と言ったとします。
でも、「使いやすい」の意味は?
- 操作ステップが少ない?
- UIが見慣れている?
- ヘルプがすぐ見つかる?
また、「安心感がある」という言葉も、金融アプリと医療機器、車内空間では、まったく異なる意味を持ちます。UXリサーチャーが向き合うのは、言葉そのものではなく、その言葉が使われている状況です。言葉は、状況や文化、習慣によって柔らかく形を変える、まさにウィトゲンシュタインが指摘した通りです。
実務における活かし方
実際のプロジェクトでも、こうした視点は多くの場面で活かされています。
- インタビュー設計では、あえて使いやすい、便利、安心といった曖昧な表現を使い、ユーザーの中の定義を引き出す
- 発言分析では、言葉の出現回数ではなく「どういう文脈で使われたか」に着目する
- UI評価では、ユーザーの言葉と設計側の意図にズレがないかを確認する
表面的な言葉を鵜呑みにせず、その奥にある意味の構造を観察すること。それこそが、リサーチから本質的な示唆を導く鍵なのです。
おわりに:じゃんけんが教えてくれるUXの本質
UXとは、ユーザーインターフェースだけでなく、人が自然に意思決定できる体験すべてを含みます。 じゃんけんには、UXの原則が自然なかたちで組み込まれているのです。
- 対立を最小限にし、迅速に合意できるプロトコル
- 地域差があっても破綻しない、ゆるやかな共通ルール
- 子どもでも直感的に理解・習得できるインタラクション設計
私たちUismは、UXリサーチの専門家として、日々「人がどのように意味をつくり、理解し、行動しているか」を観察しています。じゃんけんのような、当たり前すぎて気づかない日常の行為の中にも、文化・認知・ユーザー体験が複雑に交差しています。
UXリサーチとは、「使いやすさ」だけではなく、「意味が通じているか?」「その意味はどうやって生まれたのか?」を問い直す営みでもあります。 UXとは、遠くにある特別なものではなく、いつもそばにある「当たり前」の中に、静かに潜んでいるものなのです。
身近な文化やふるまいをヒントに、より良いUXを一緒に探してみませんか? ご相談・ご質問はいつでもお気軽にどうぞ。