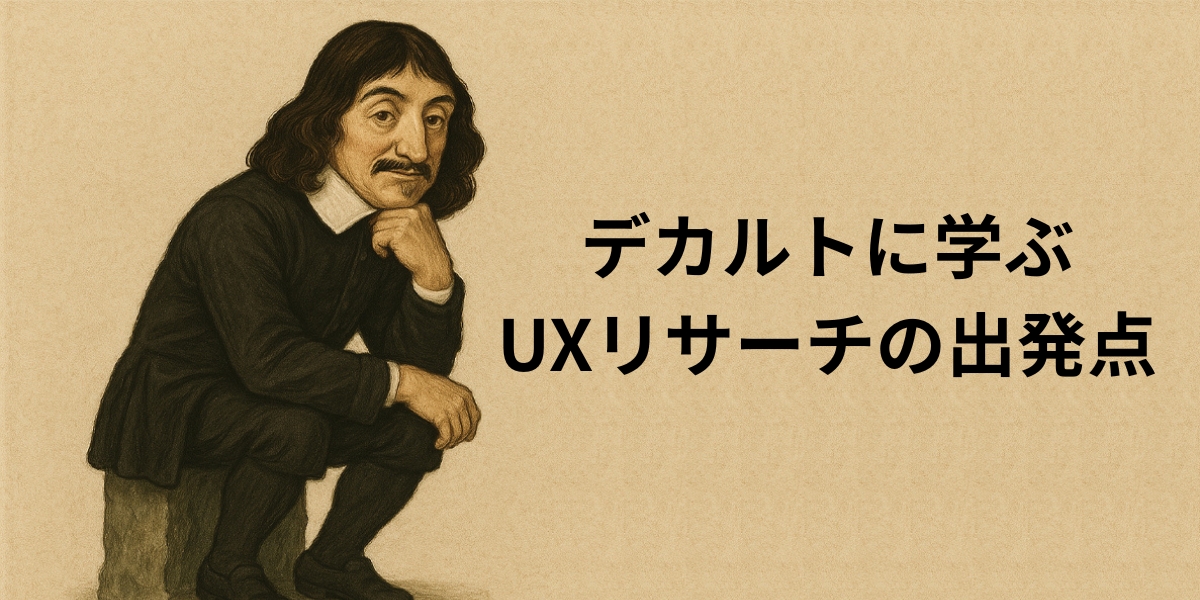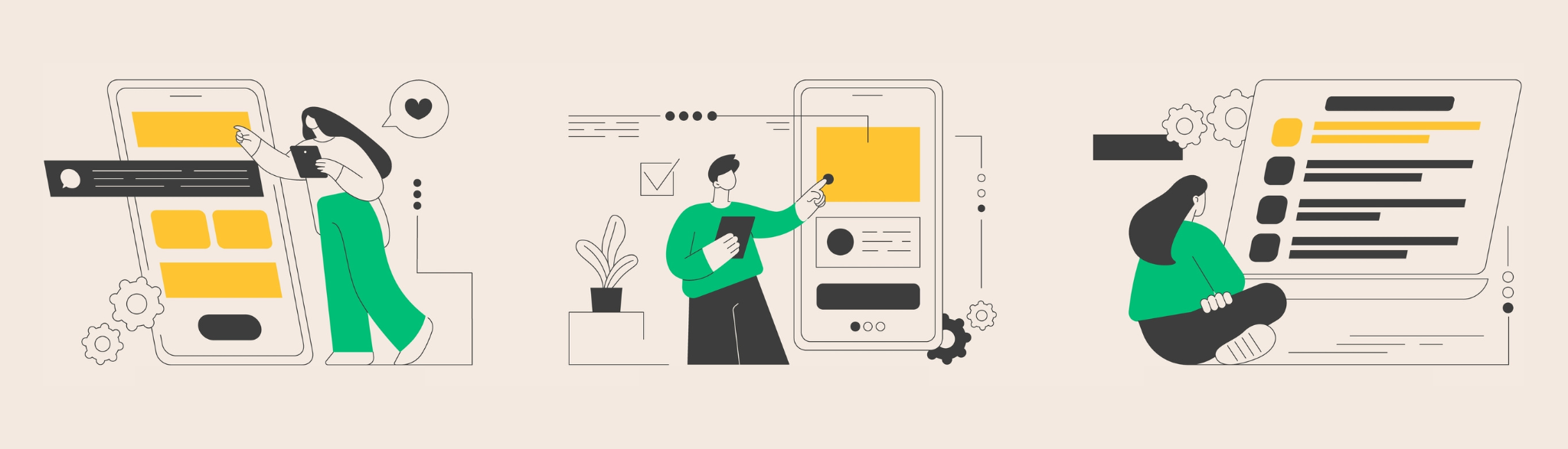17世紀の哲学者ルネ・デカルトが残した、あまりにも有名な言葉がある。
「我思う、ゆえに我あり」
これは、自らの存在証明に留まらず、徹底的な懐疑の果てに、揺るぎない確実なものを見つけ出そうとする、知的探求の出発点を示す言葉です。そしてこの問いは、数百年の時を超え、現代の私たちにとっても決して他人事ではありません。この数百年前の哲学者の探求は、驚くほど現代の製品・サービス開発に携わる、私たちの課題と重なります。
数ヶ月を費して作り上げた、新しい予約システムのプロトタイプ。開発チームは、その完成度に絶対的な自信を持っていました。「このフローは直感的で、誰でも迷わないはずだ」と。しかし、最初のユーザーテストで、その確信はもろくも崩れ去ります。ユーザーは全く想定外の行動をとり、核心的な機能にたどり着けず、途中で諦めてしまいました。
チームを包む、重い沈黙。「私たちの信じていた“常識”は、いったい何だったのか?」
この確信の崩壊の瞬間こそ、デカルトが経験した徹底的な懐疑であり、真のUXリサーチが始まる場所なのです。
すべてを疑うUXリサーチのマインドセット
デカルトは、確実な真理に到達するために、まず方法的懐疑という姿勢を取りました。自らの五感、常識、そして目の前に机が存在することさえも、「本当に正しいのか?」と徹底的に疑う。その目的は、すべてを破壊することではなく、疑い抜いた先に残る、絶対に揺るぎない確実なものを見つけ出すことでした。
この姿勢は、プロダクト開発における作り手の認知バイアスを乗り越えるために、驚くほど有効です。私たちは、「自分たちと同じようにユーザーも考えるはずだ」という偽の合意効果や、知り尽くしているがゆえに初心者のつまずきを想像できなくなる専門家の呪いに、常に囚われています。

優れたUXリサーチャーは、楽観的な創造者である前に、まず謙虚な懐疑論者でなければなりません。「私たちの仮説は、間違っているかもしれない」と、自らの常識を疑うところから、すべては始まります。
ユーザビリティテストの本質
デカルトは「感覚は、我々を欺くことがある」と述べました。これは、UXデザインの現場で日々起きていることです。
「このボタンは色が違うから、ユーザーは絶対に見つけてくれるはず」
「このアイコンの意味は、誰が見ても明らかだろう」
こうした作り手の視覚的な常識や感覚は、いとも簡単に裏切られます。この思い込みの罠から私たちを救い出してくれるのが、ユーザビリティテストです。
ユーザビリティテストとは、実際のユーザーに製品やプロトタイプを操作してもらい、その行動を観察することで、設計上の問題点を発見するためのシンプルな手法です。しかし、その本質は、作り手の感覚という名の仮説を、ユーザーのリアルな行動と突き合わせることにあります。
テストを実施すると、ユーザーは私たちの想像を遥かに超えて、情報を見落とし、言葉を誤解し、全く異なるロジックで行動します。そこで得られる、時に残酷なほどの観察事実こそが、私たちを思い込みから解放し、真実へと導いてくれるのです。
観察データという“小さな確実性”
すべてを疑ったデカルトが、最後にたどり着いた揺るぎない第一原理が、「我思う、ゆえに我あり」でした。「疑っている私自身の存在だけは、疑いようがない」という確実性です。UXリサーチにおける「我思う、ゆえに我あり」とは、反論のしようのない「観察データ」に他なりません。ユーザーが何を言ったかではなく、「何をどう行動したか」に根ざした、動かしがたい事実。それが、私たちにとっての出発点です。
- 確実性1:5人中5人のユーザーが、フィルター機能の存在に最後まで気づかなかった。画面の左側に常に表示されていたにもかかわらず、目を向けることなく、希望条件と合わない宿泊先の一覧をひたすらスクロールしていたのです。
- 確実性2:ユーザーは「同期」という言葉を、例外なく「バックアップ」のことだと誤解した。彼らは、クラウドとローカルが常時連携していることを理解できず、「消えたら困るから、念のため同期しておこう」とコメント。この誤解は、専門用語がいかにユーザーの文脈とズレやすいかを示しています。

このような目の前で起きた事実は、ユーザーの多様な感覚や文脈が反映された「観察可能な確実性」であり、統計的な証明ではなくても、設計上の意思決定において、極めて価値あるインサイトとなります。
理性ではなく“行動”を信じる
このアプローチは、ユーザビリティ研究の世界的権威であるヤコブ・ニールセンが提唱した「N=5テスト」の考え方とも通じます。彼は、わずか5人のユーザーにテストするだけで、ユーザビリティ問題の約85%を発見できると主張しました。統計的な網羅性ではなく、定性的な観察から得られる「小さな確実性」の積み重ねこそが、UXの改善には不可欠なのです。
ただし、ここでデカルトの探求とUXリサーチの間には、決定的な違いが生まれます。デカルトは、感覚すらも疑い、最終的に純粋な「理性による確実性」へと向かいました。一方で、UXリサーチャーが基盤とするのは、ユーザーの「行動という、観察可能な確実性」です。私たちは、ユーザーの五感を通して現れる行動こそを、最も信頼できる真実の出発点としています。壮大で美しい仮説から始めるのではなく、小さな確実性を一つひとつ謙虚に積み上げていくこと。それが、砂上の楼閣ではない、堅固なユーザー体験を築くための唯一の道です 。
おわりに:確信から検証へ
UXリサーチャーにとって、デカルトの方法的懐疑とは、知への謙虚さの哲学的表現に他なりません。自分たちがまだ何も知らない、という前提に立つことです。作り手は、常に「我思う(=こうすれば、きっとうまくいくはずだ)」と確信を抱きます。しかし、デカルトがその「我思う」すら疑ったように、その確信こそが最も危険な罠になり得ます。だからこそ、私たちはこう結論づけるのです。
「我思う、ゆえに我テストする」
最良のUXは、「確信」からではなく、「検証」から生まれるのです。Uismでは、このデカルト的な懐疑の精神を大切に、「当たり前」を疑うことからユーザーの真実を探求する旅をご支援します。これまで国内外の多様な業界で、数多くのユーザビリティテストを通じて、作り手の「思い込み」を、観察事実という「確実性」へと変えるお手伝いをしてきました。
もし貴社の「当たり前」を、一度ユーザーの真実と照らし合わせてみたいとお考えでしたら、ぜひ一度、お気軽にお声がけください。
参考文献(外部リンク)
関連記事
開発のスピードと検証の質を両立させるRITE(Rapid Iterative Testing and Evaluation)手法。小さく素早くテストを重ねながら、UXを改善していくアジャイルなアプローチをご紹介します。