「ユーザーに考えさせるな(Don’t make me think)」
スティーブ・クルーグの名著『Don’t Make Me Think』(邦題:『ウェブユーザビリティの法則』)のタイトルにもなっているこの言葉は、長らくUI/UXデザインにおける黄金律でした。 ユーザーの手間を省き、迷わせず、最短距離でゴールへ導くこと。それが「良いUX」であると、私たちは信じて疑わないことでした。しかし、生成AIが私たちの仕事を代替し始めた今、あえて問い直したいのです。 楽な体験を提供し続けることは、本当に人間のためになっているのでしょうか?
「神は死んだ」と宣言し、既存の価値観をすべて破壊した哲学者フリードリヒ・ニーチェ。 彼の視点を借りるならば、今のUXデザインは、人間を堕落させる装置になりかねません。
「末人」化するユーザー体験
ニーチェは代表作『ツァラトゥストラはこう言った』の中で、「末人(Letzter Mensch)」という存在を描きました。末人とは、冒険や創造を放棄し、安楽と平穏だけを求める人間です。彼らは苦痛を避け、リスクを嫌い、ただ日々を快適に過ごすことだけに満足する。「私たちは幸福を発見した」と言って、まばたきをする存在です。
現代のデジタルプロダクトが提供する体験は、かつてないほど快適で滑らかです。しかし、その心地よさは、無意識のうちに私たちを「末人」へと導いてはいないでしょうか。おすすめに従うだけで商品が届き、ワンクリックでコンテンツを消費する。そこには迷いも苦労もありませんが、同時に意志も成長もありません。過保護に設計された「摩擦のないUX」は、その快適さと引き換えに、ユーザーを無力な受信者へと変えてしまう危うさをはらんでいます。
「使いやすさ」よりも「万能感」を
ニーチェは、末人と対極にある理想的な存在として「超人(Übermensch)」を提唱しました。超人とは、現状の自分を乗り越え、自らの意志で新しい価値を創造していく存在。その根底にあるのが「力への意志」であり、自分の力を高め、発揮したいという根源的な衝動です。AI時代のUXが目指すべきは、ユーザーを「楽」にすることではなく、この「力への意志」をいかに満たせるかが、今後ますます重要になっていくのではないかと我々は予感しています。
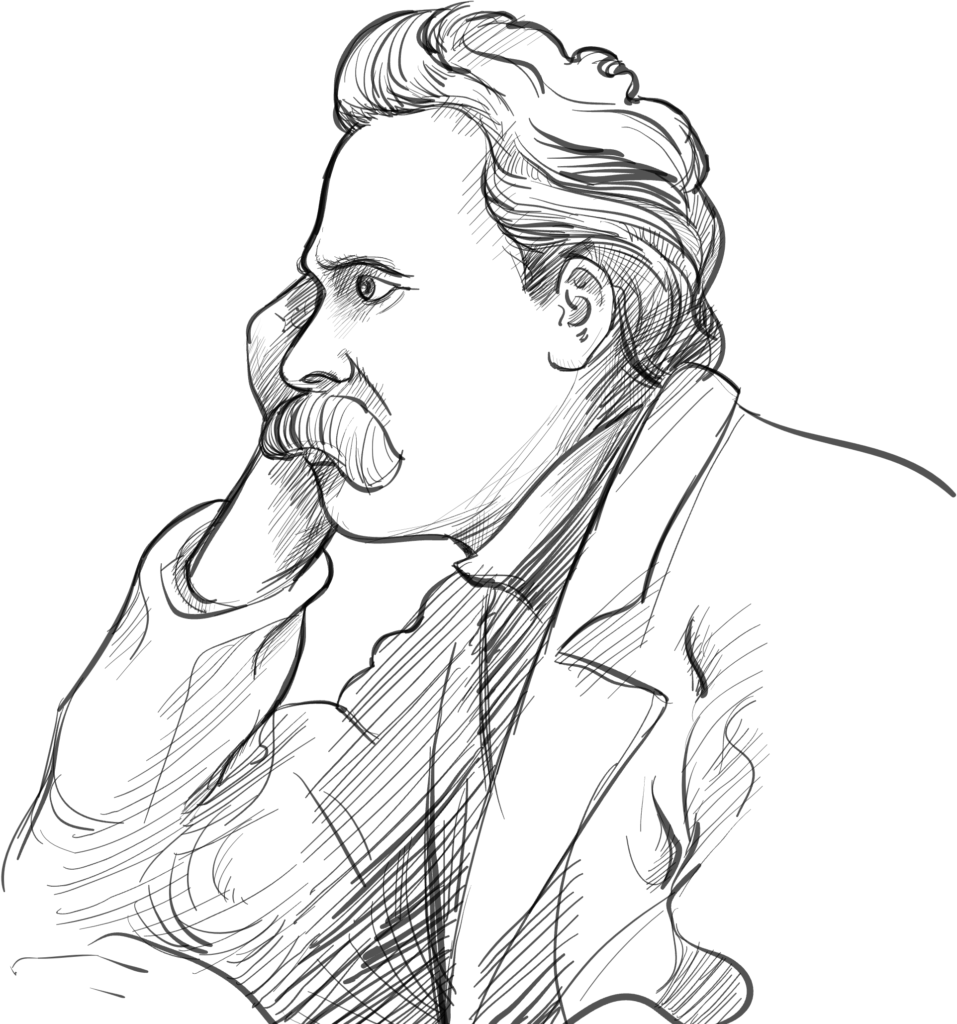
例えば、Adobe Photoshopに搭載されたAI機能「ニューラルフィルター」を見てみましょう。AIは一瞬で「表情を変える」「肌を滑らかにする」といった高度な補正を提案しますが、そこで終わりではありません。ユーザーはスライダーを操作し、AIの提案を自分の意図に合わせて微調整し、最終的な絵作りを行います。最初は各パラメータの意味を理解するのに学習コストがかかるかもしれません。しかし、試行錯誤の末にAIを完全に制御下に置いた時、ユーザーはAIにやってもらったのではなく、「自分の表現力が飛躍的に広がった」という強烈な万能感を得ます。
もちろん、Photoshop自体はAI以前から存在するプロツールです。直感的に使えるわけではなく、習得には一定の苦痛も伴います。しかし、そこにAIが加わることで、より広範で自由な表現の可能性が拓かれ、ユーザーは使いやすいから好きではなく、自分の力で使いこなしていると実感できるのです。これこそが、ニーチェ的な意味での「優れたUX」です。単なる使いやすさではなく、能力の拡張もまた、これからの重要な指標になっていくのではないでしょうか。
AIは「代行」か、それとも「拡張」か
今やAIは、特別なツールだけでなく、あらゆるプロダクトやサービスに当たり前のように組み込まれ始めています。 だからこそ、次の「どちらの方向を向くか」という視点は、すべてのデザインにおいて決定的な差となります。
代行型:
面倒な作業をAIが肩代わりする。
「あなたは寝ていていいですよ」というアプローチ。
拡張型:
人間の能力をAIが増幅させる。
「あなたには翼がありますよ」というアプローチ。
代行型は便利ですが、ユーザーを末人化させます。一方で拡張型は、ユーザーを超人化させます。
文章作成AIを例にとりましょう。「勝手にメールを書いて送信しておく機能」は代行型です。 対して、「自分の断片的なアイデアを、論理的な構造に変換して壁打ちしてくれる機能」は拡張型です。後者を使った時、ユーザーは「AIのおかげで楽ができた」ではなく、「自分はこんなに思考を深められるのだ」という自己肯定感を感じます。AIを、人間を甘やかす代行者(執事)にするのか、それとも人間を強くする拡張のパートナーにするのか。 UXデザインは今、その岐路に立たされています。
すべてのプロダクトは「超人」を目指すべきか?
もちろん、すべてのUXが等しくユーザーの能力拡張を目指すべきだ、というわけではありません。日々のルーチンワークを淡々と処理する管理画面や、公共の手続きなどにおいては、ユーザーの認知負荷を極限まで下げる「静かな支援」こそが、依然としてUXの正義であり本質の一つです。しかし、生成AIやクリエイティブツール、あるいは高度な意思決定を支援するダッシュボード、つまり人間の思考や創造に関わる領域においては、もはや単なる利便性だけでは不十分です。
ユーザーがそのツールを使った結果、以前の自分より進化したと感じられるかどうか。 この視点こそが、コモディティ化するAIプロダクトの中で選ばれ続けるための、設計と評価のカギとなっていくはずです。
「摩擦」を恐れないリサーチへ

もし、私たちがユーザーを「超人」にしたいと願うなら、UXリサーチの手法も変えなければなりません。従来のユーザビリティテストでは、「どこで詰まったか」「どこで時間がかかったか」という負の摩擦を徹底的に潰すことが正義でした。 しかし、能力拡張のためのツールにおいては、適切な「正の摩擦」が必要になることもあります。
その難易度は、ユーザーの挑戦意欲を掻き立てているか? そのプロセスを経ることで、ユーザーは以前の自分より強くなったと感じているか?
私たちはリサーチにおいて、単なる快適さだけでなく、効力感や支配力といった感情を評価する必要があります。 「ペインポイント」を取り除くだけでなく、「パワーポイント(力が湧く瞬間)」を見つけ出すこと。私たちは、そこに次世代のUXリサーチの可能性があると考えています。
終わりに
私たちは、どちらに進むのか。
ニーチェは言いました。 「人間とは、動物と超人との間に張り渡された一本の綱である」
今のままで留まるのか、それとも向こう側へ渡るのか。 AIという強力なテクノロジーを手にした今、UXデザインは単なるインターフェースの設計を超えて、人間の進化の設計へと領域を広げています。
プロダクト・サービスは、ユーザーを弱くも強くもします。それは単なる二択ではなく、どれだけ自己変容の余地を生み出しているかという問いです。貴社のプロダクト・サービスは、ユーザーにどんな変化の可能性を開いているのでしょうか。
「使いやすさ」の先にある、ユーザーの能力拡張を科学する。そんなUXリサーチについて、ぜひ私たちと対話を始めませんか?
関連記事:
本稿で述べた「パワーポイント」を見出すために、AI時代のUXリサーチャーはどのような人間理解を深めていくべきかを探求します。
本稿で提示した「ユーザーを“超人”にする」という思想を、実際のAIプロダクト開発で成功させるための具体的な「UX3原則」へと落とし込み解説します。



